新暦で6月21日ころ。 夏至は、北半球では一年で最も昼の時間が長く夜が短い日です。 日本では梅雨の最中で、一年で農耕の黄金期と言っていいでしょう。 夏至を過ぎると、気温はさらに上昇し夜が長くなり始め昼が短くなる。 最も陽… 続きを読む 夏至
夏至


新暦で6月21日ころ。 夏至は、北半球では一年で最も昼の時間が長く夜が短い日です。 日本では梅雨の最中で、一年で農耕の黄金期と言っていいでしょう。 夏至を過ぎると、気温はさらに上昇し夜が長くなり始め昼が短くなる。 最も陽… 続きを読む 夏至

新暦で6月6日ころ。 芒種は民間では「忙種」とも言われる。芒は麦や稲など穂を付ける植物の穂先の突起のことです。 そんな麦や稲の種を蒔いたり植えたりする時期がこの芒種です。 つまり、芒種は農業生産と密接に関連する節気です。… 続きを読む 芒種

新暦で5月21日ころ。 小満は夏の第二の節気です。 この時期には、夏に熟成する様々な作物が豊かになりつつあるがまだ完全に成熟には至らない、 そんな時期にあたります。「小満」の名はここからきたものでしょう。 草木が天地に繁… 続きを読む 小満

新暦で5月5日ころ。 立夏は夏の最初の節気で、北半球が夏になることを示します。 農作物はすくすくと成長し始めるころです。 どんどん夏が近づいて新緑がまぶしく心地よいとても柔らかな陽気で、 さわやかな風が吹く五月晴れの季節… 続きを読む 立夏

萍始めて生ず。鳴鳩其の羽を払い、戴勝桑に降る。 穀雨は春の最後の節気であり、穀雨を得て萌えることを意味する。 穀雨の頃、ますます暖かくなり、降水も増える。 花が咲き木々が茂り、生気が一番あふれる。穀雨を過ぎると、 陽気が… 続きを読む 穀雨

桐始めて華さき、田鼠化して鴽と為り、虹始めて見ゆる。 清明は二十四節気の第五の節気である。清明の時節、春もたけなわの頃であり、 万物が新鮮な空気を吸い、まさに春和景明のさまとなる。 清明には古来お墓詣りとの習俗があり、先… 続きを読む 清明

玄鳥至る。雷乃ち声を発し、始めて電す。 春分は春の九十日間を二等分する日で、二十四節気の四番目である。 春分の日、太陽が赤道を直射し、昼夜が均等して寒暑が均衡する。 春になると体がだるく、眠くなりがちだ。こうした春の眠た… 続きを読む 春分

桃はじめて花咲き うぐいす鳴き 鷹化して鳩となる 新暦3月5日ころ。 冬ごもりしていた虫が春の暖かさを感じて地中から這い出してきます。 引きこもりが開くことを啓蟄といいます。一雨ごとに春の気配が訪れます。 雨水の節気から… 続きを読む 啓蟄
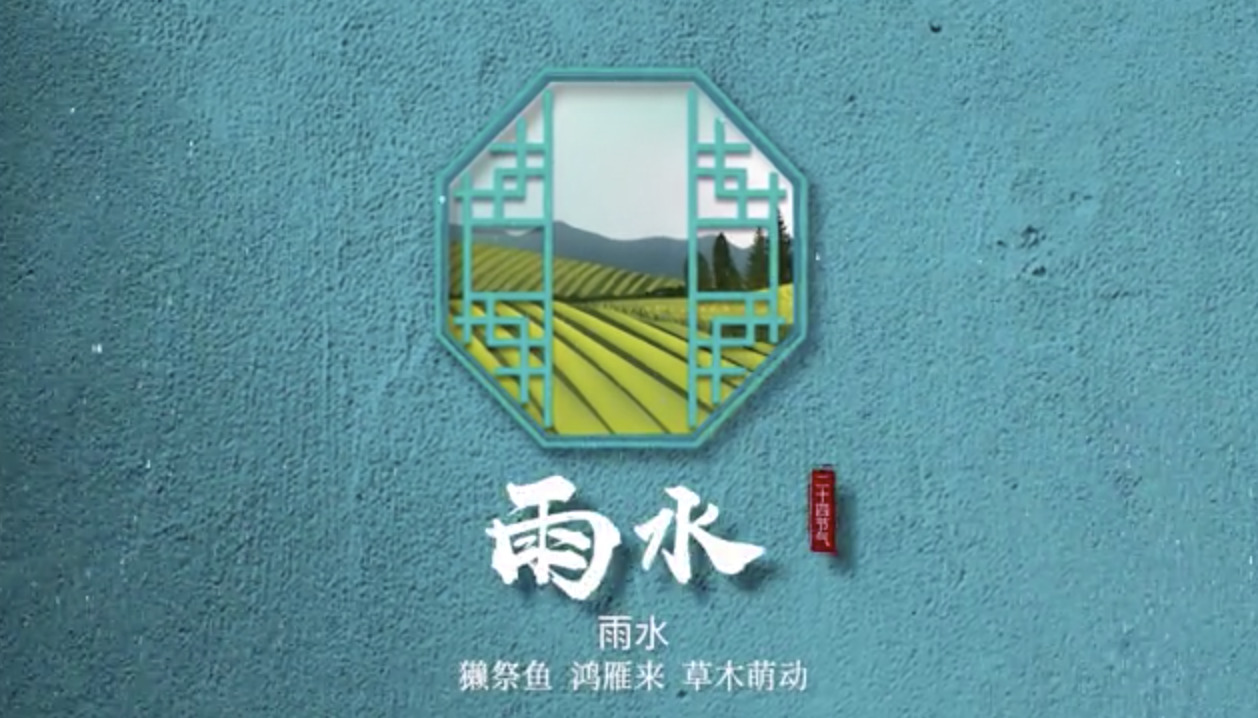
好雨時節を知り、春にあたりて乃ち発生す 2月18日ころ。降る雪が雨へと変わり、このころから雪解けが始まるころです。実際にはまだ雪深いところも多く、これから雪が降り始める地域もありますが、ちろちろと流れ出す雪解け水の音に… 続きを読む 雨水

新暦で2月3日ころ 1年を24の節に分けた二十四節気の最初の節気です。 旧暦の新年ですが今の暦では、おおよそ毎年2月4日です。 暦の上ではこの日から春になり、その前日は豆をまいて邪気を払う節分です。 この節分は「節を分… 続きを読む 立春